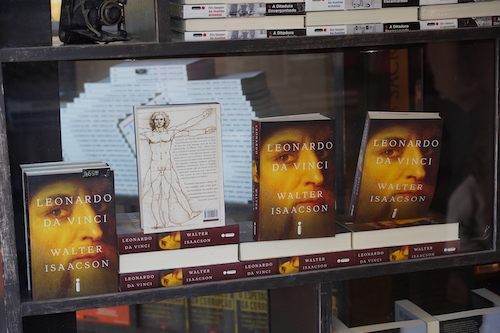B'zの歌詞を詳しく読み解いていくと、魂のぶつかり合いなどといった仏教の価値観を意識させる部分などがあって、神秘的な気持ちになることがよくあります。
B'zの稲葉浩志さんは、高校時代、数学の模試で全国に3位になるほど、数学が得意だったそうですが、数学と音楽を極めると目には見えない「世の中の調和」を読み取れるようになるのだと言う。
少し前に流行った「のだめカンタービレ」という漫画の中に次のようなフレーズがあります。
「1500年くらい前は、神の作った世界の調和を知るための学問が、天文学、幾何学、数論、音楽だったんだ。」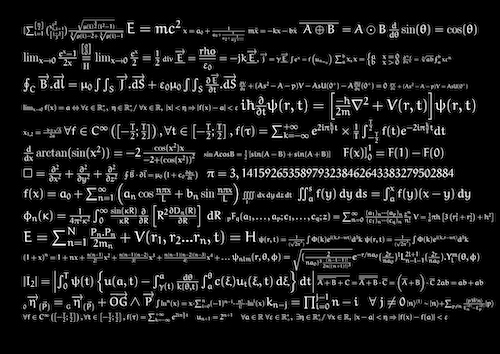
↑神の作った世界を知るためには、数学が必要。
音楽は、人間の感性を通じて、喜び、悲しみ、憧れ、勇気、落胆などの心の有様を表現するのに対し、数学は、人間の知性を通じて、自然現象や社会現象がどのように見えるかを表現していく。
歴史を振り返れば、ハンマーで金属を叩く音を聴いて、「ドレミファソラシド」といういわゆる音階を最初に発明したのは、数学者のピタゴラスでした。
芸術家のレオナルド・ダ・ヴィンチは、自然の美しさの背後にある法則を数学の知識を使って理解しようとし、アップルの「マッキントッシュ・プロジェクト」の最初のリーダーであったジェフ・ラスキンは、数学と哲学の学位、そして、音楽プログラムの研究でコンピュータサイエンスの修士を持っていた。(1) (2)
恐らく、芸術の感性と数学の知識が組み合わさると、一つ上のクリエイティビティにアクセスできるようになるのだろう。
↑自然の美しさの背後にある法則を数学で理解しようとする。(Pic by LC)
音大を卒業しても、音楽で食べていける人は数パーセントなのだと言います。また、大抵の学生たちは、「数学の知識なんて世の中に出てから、何の役に立つの?」と思っていることだろう。
数学と芸術は常にハーモニーを描いていて、恐らく、宇宙や「目に見えない世界」というものなども、数学と芸術のハーモニーの中に存在している。
ご飯とおかずを別々に食べても食事を楽しめないのと同じように、「数学は数学」、「音楽は音楽」と言った感じで別々に学んでいっても、世の中の調和を理解することはできない。
↑数学と芸術は常にハーモニーを描く。(Pic by LC)
学校の授業も、オンラインで勉強することが当たり前になれば、学校の退屈な数学の授業よりも、もっと、面白い視点で数学を教えてくれるYoutuberから数学を学びたいという子供も増えてくることだろう。
B'zの歌から感じる神秘性は、音楽と数学の世界で表現された、一つの次元の高いクリエイティビティなのかもしれません。
Note
1.ウォルター・アイザックソン『レオナルド・ダ・ヴィンチ』文藝春秋、2022年 2.竹内 一正『イーロン・マスクはスティーブ・ジョブズを超えたのか』PHP研究所、2022年
参考書籍
■KDDI ∞ Labo『スタートアップス 日本を再生させる答えがここにある』日経BP、2022年