
不況が深刻化し始めると、将来、子供には苦労をさせたくないと、名門学校への進学率がどんどん上がっていきますが、中でもハーバード大学やコロンビア大学などを含む、アメリカのアイビー・リーグへの入学は年々難しくなっており、合格率はハーバード大学が5.8%、イェール大学が6.72%、そしてコロンビア大学は6.89%と、狭き門をくぐり抜けるために、激しい戦いが毎年のように繰り広げられているようです。
高い目標を持つ人達は、その分野で最も権威のある組織に入ろうとしますが、アメリカの作家、マルコム・グラッドウェルによれば、一流大学の落ちこぼれよりも、二流、三流大学のトップでいる方がよい時もあるとして、社会の本流から外れると不利なことも多いが、逆にそれが利点になることも多くあると指摘しています。(1)
↑不況になればなるほど、名門大学への進学率は上がる。
なぜなら、一流の機関であればあるほど、周りに優秀な学生が多いため、自分自身の能力を低く評価してしまう傾向にあり、そこそこの高校で優等生だった生徒は、エリート大学に入ったとたん、劣等感を感じるようになると言いますが、実際、高いハードルを乗り越えたり、困難な問題に取り組んだりする意欲を支えるのは、自分はこれだけできるという「セルフイメージ」の影響が大きく、良いセルフイメージが描けないと、やる気も自信も出てこないと言います。
例えば、数学の天才で、自分よりも数学で右に出る者はいないと思っていたビル・ゲイツは、高校生の時点で、全国トップレベルの数学の知識を身に付けていましたが、ハーバード大学に進学すると、16歳で博士号を取った教授の授業で、最大限の努力をしたにも関わらず、“B”の成績しか取れなかったことに落胆し、数学に対するやる気を失ってしまい、専攻を理論数学から応用数学に変更してしまいました。(2)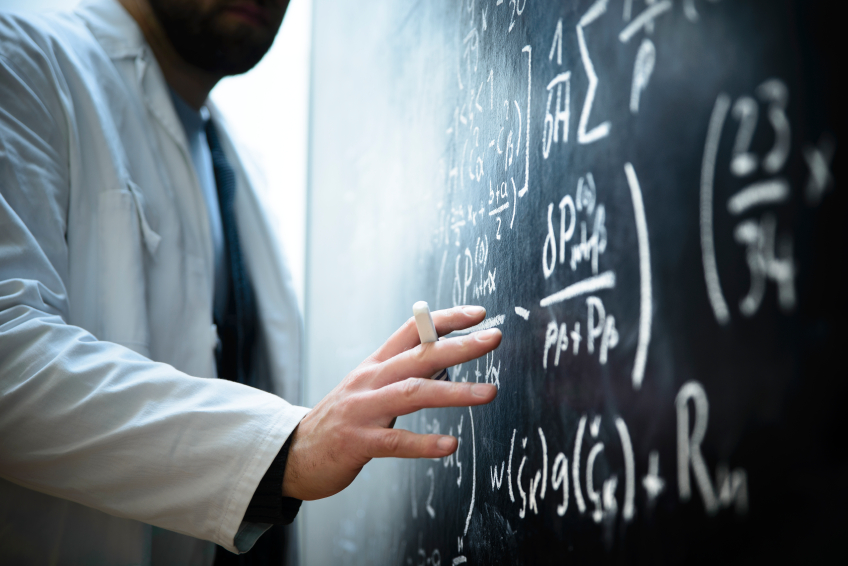
↑ビル・ゲイツは数学に関して、100万人に1人の天才だが、ハーバードには1000万人に1人という超天才がいる。
現在、テクノロジー分野への感心が高く、理系の学位を持っていれば、様々な業界で有利なのは間違いありませんが、アメリカでは、科学やテクノロジー、そして数学といった理系科目を専攻した学生の半数以上が、1年生か2年生で退学や転部をしており、これがアメリカでエンジニアが不足している大きな原因になっていると言います。
マルコム・グラッドウェルがニューヨーク州にあるハートウィック大学(普通の大学)と名門ハーバード大学を対象に調査した内容によれば、ハートウィック大学の上位の生徒とハーバード大学の下位の生徒の学力レベルはほぼ互角ですが、ハートウィック大学の上位の生徒の大多数は望み通り、エンジニアや生物学者になれるのに対し、ハーバード大学の下位の生徒はやる気を無くして、文系に転部する人が続出するだろうと分析しています。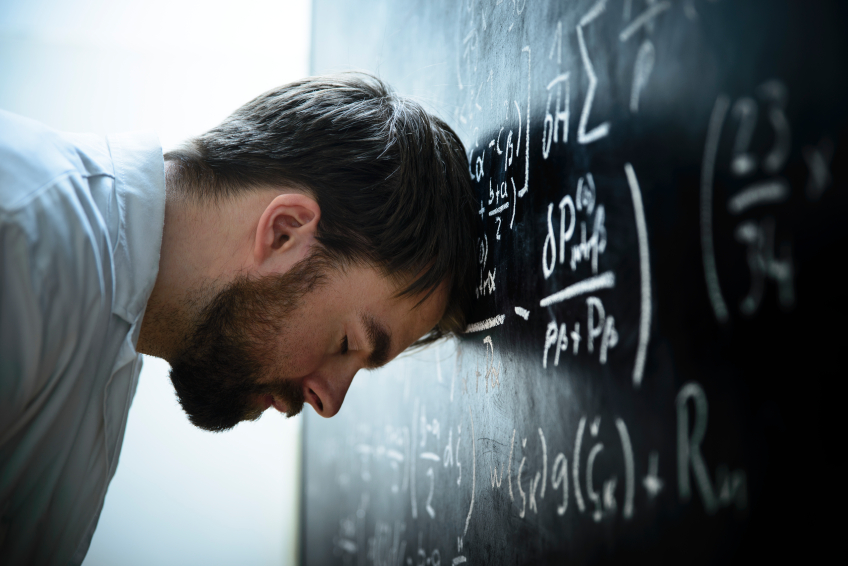
↑一流の小者になるか、二流の大物になるか、十分によく考える必要がある。
これは国別の幸福度と自殺率の関係を見ても同じことですが、例えば、スイス、デンマーク、アイスランド、オランダ、そしてカナダなどの国は、世界で最も幸福度が高い国々なのに対して、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインの幸福度は比較的低いのにも関わらず、自殺率が高いのは前者の幸福度が高い国々だと言います。
つまり、不幸な国では、自分に災難が襲ってきても、それほど落ち込みませんが、周りがみんな幸せそうにしていたら、不幸を一層強く感じてしまうのと同じように、理系の学位が習得できるかどうかは、本人の頭が良い悪いではなく、クラスメイトに比べて、自分の頭が良いか悪いかに大きく依存する傾向にあるようです。
↑幸福度が高い国では、それに比例して自殺率も高い。
カリフォルニア大学のミッチェル・チャンが行なった調査によれば、条件がすべて同じだったと仮定した場合、大学のSAT(大学能力評価試験)のスコアが10ポイント下がるごとに、理系学位の取得率は2%上昇するらしく、さらに博士号を習得した後に、権威のある学術雑誌に掲載された論文の数は、ハーバードやMITなどのトップスクールを卒業した「普通、もしくは普通以下」の人よりも、名前すら聞いたことのない底辺大学をトップで卒業した生徒の方が、論文の掲載回数は多いのだと言います。
↑名門大学でモチベーションが高いのはトップの人達だけ。
これは、あなたが人を採用する立場にいるのであれば、一流大学の普通、もしくは普通以下の人を採用するべきなのか、それとも、二流、三流大学のトップの人を採用すべきなのか良く考える必要がありますが、あるウォール・ストリートの銀行は、近年トップスクールの生徒の獲得が難しく、ある時期から二流、 もしくは三流の大学から優秀な人を採用する方法に切り替えたところ、素質の高い人達を集めることができていると述べていますし、グーグル人事担当上級副社長のラズロ・ボックは本当に特別な知識を必要とするポジションは当然学歴が重要になってくるが、チームのメンバーとして何か困難な問題に取り組む場合などは、学歴はそれほど重要ではないとしています。
↑実際、チームワークや問題解決にはあまり学歴は関係ない。
実際、難関校への進学でセルフイメージが上がるのは子供ではなく親だけで、最近では、難関校の良いところ、悪いところをしっかり理解せずに、進学先を決めてしまう親や学生が多すぎると言います。
これは、大きな会社に入って巨大システムの歯車になるよりも、小さな組織で好きなだけ暴れてやろうという考えにも似ているのかもしれませんが、どんなクラスや組織にも底辺層が必ず存在するため、周りの人達に影響されてやる気を失ったり、才能を開花し損ねてしまうのであれば、それは個人にとっても、世の中にとっても、もの凄く勿体無いことであるということは間違いありません。
とりあえず、「大きな池の小者はやる気を失い、小さな池の大物はやる気を出す。」という社会的成功の奇妙な関係は、覚えておいて損はなさそうな気がします。
1.マルコム・グラッドウェル「逆転! 強敵や逆境に勝てる秘密」(講談社、2014年) Kindle P840 2.ポール・アレン「ぼくとビル・ゲイツとマイクロソフト アイデア・マンの軌跡と夢」(講談社、2013年) Kindle P1657
※主な参考:マルコム・グラッドウェル「逆転! 強敵や逆境に勝てる秘密」(講談社、2014年)
